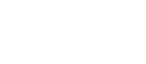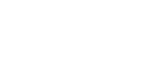�ک`���α��ĤǤ���
���N�ι���֪�����¤������������kҊ������ˎڤ���Ϣ��������ι�h���ؤ��m�꣭
2021��6��16�ո���







����ѧ�о����������h���о�����������ѧ���|��������ѧ
ˮ�b�о�?�����C�����|����ѧ�������ˮŮ�Ӵ�ѧ
������ѧ�о��������У��h���YԴ��ѧ�о����`�ϳɥ��Υߥ����о�����`�פ��ɾ��ϥ���`�ץǥ��쥯���`���P���ɲ����ϼ��о��T������ݽ����о��T�������h���о�������������I��κӵ��������L��ɽ����������о��T���ľ���e�о��T���о����r����������ѧ��ѧԺ��ѧ�о��Ƥγɴ����v�����о����r���F�������|��������ѧ���ڣ�����Ҋ��˾�������̣��о����r����ˮ�b�о�?�����C��ˮ�b���g�о����ζ��x���о��T���о����r�����|����ѧ��ѧԺ�rѧ������ѧ�о��Ƥμ���������̡������ˮŮ�Ӵ�ѧ�������������ڤ�ι�ͬ�о�����`�����ϡ�2012�꤫��2014��ˤ����Ɩ|���ط����ذ�?�_����ǵä�줿�����˥������Υ�ǩ`�������ä�������ˎڤ��ֲ��������夫�����N�ι���֪������Ҏ�ι�������[1]��kҊ���ޤ�����
�����о��ɹ��ϡ�����ˤ���������ι����ݥᥫ�˥���ȹ���������M���ν�����ؕ�פ��뤳�Ȥ��ڴ�����ޤ���
������ζय�ϡ���������Τ���˹�����ä�����Ƿ�Ǥ���̫ꖹ�γɷ֤Τ�������ɫ��Ϻ���ޤǽ줭�ޤ�������ɫ��Ͻ줭�ޤ����Τ��ᡢ�N���������Ϣ���뺣�������ˤȤäơ����ޤ��ޤʲ��L�ι���֪����������夬��Ҫ�Ǥ���
����ͬ�о�����`�פϡ��������Υ�[2]�ǩ`�����ä�����ɫ��������Υ���ץȥ�����[1]�z�������Ф�̽���ӤȤ��ƽ������ޤ����������ơ�����ץȥ�����ȸߵ�ֲ��ˤ������ɫ��������Υե��ȥ�����[1]���ںϤ����z���Ӥ�kҊ���������z���������Υ���ѥ��|���ǥ奢�륯���ࡹ���������ޤ������ǥ奢�륯����ϡ���ɫ�⡢��ɫ�⡢�h��ɫ����֪�Ǥ��������[������Υץ饷����[3]��һ�N�Ǥ���ԥ��Υ��å���[3]�Ȥ��ν��F�N���������Ф��Ƥ��뤳�Ȥ��֤���ޤ���������ˡ��ԥ��Υ��å����Υ��Υ����Ф���ȫ���i�����ԥ��Υ��å����������Фǹ�ΤۤȤ�ɽ줫�ʤ��й���²����麣���ӤޤǤζ����ʹ�h�����m�ꤷ�Ƥ������ɤ�һ�ˤ����餫�ˤ��ޤ�����
�����о��ϡ�����饤���ѧ�j�I��Nature Communications����6��16�ո����ձ��r�g6��16�գ��˒��d����ޤ���

�����[�ԤΥץ饷�����һ�N�ԥ��Υ��å���
����ͬ�о�����`��
| ����ѧ�о��� �h���YԴ��ѧ�о����` �ϳɥ��Υߥ����о�����`�� | |
|
������`�ץǥ��쥯���` |
�ɾ� �� ���ޤĤ� �ߤʤߣ� �P�� �ɲ��ӣ��ޤ��� �椦���� ��ԭ ־�� ������Ϥ� �椭���� ���� �ݽ��ӣ����ޤ� ���Ĥ��� ��ԭ �{���ӣ�����Ϥ� ���ߤ��� �I�� Ӣʷ ���Ϥޤ��� �ҤǤդߣ� ��ɽ ���� �������� �Ȥ⤳�� �վ� ���� �������Ҥ� ���䣩 |
| �����h���о��� ����������I�� ����������YԴ��ȫ�о����M�� | |
| �����L ��������T ���e��T������r�� |
�ӵ� ���� ������� �ޤ��Τ֣� ɽ�� ��� ����ޤ��� �Ϥ�裩 �ľ �� �������� �������ģ� |
| ������ѧ ��ѧԺ��ѧ�о��� | |
| ���v�����о����r�� �� ���������̣��о����r�� |
�ɴ� �� ���ʤ꤫�� �줤�� �����F�������|��������ѧ ��ѧ��������ѧ�� ���ڣ� ��Ҋ ��˾ ���դ��� �������� |
|
ˮ�b�о�?�����C�� ˮ�b���g�о��� |
|
| �����L������r�� ����T������r�� |
��Ҋ ֪�� �������� �Ȥ⤳�� ���x �� ���錄�ʤ� �Ĥ褷�� |
| ����������ӥ�?���֥ɥ�������ѧ���g��ѧ | |
| ���e�������� | ��lܥ Т �������礦�ܤ� �������� |
| �|����ѧ ��ѧԺ�rѧ������ѧ�о��� | |
| ������ | ���� ���� ���褷���� �����Ȥ��� |
| �����ˮŮ�Ӵ�ѧ ��ѧ������ѧ�� | |
| �����ڣ��о����r�� ��ѧ�����о����r�� |
���� ���� �������� �ޤ������� ƽ�� �یg ���Ҥ餿 �ޤʤߣ� |
�о�֧Ԯ
���о��ϡ�����−-ˮ�b�о�?�����C���ι�ͬ�о��Ȥ����_ʼ���졢�ձ�ѧ�g�