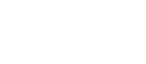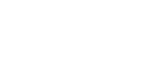ページの本文です。
平成29年度卒業式 学長告辞
2018年3月29日更新
本日、学士の学位を取得され、卒業式を迎えられた520名の皆さま、まことにおめでとうございます。お茶の水女子大学の教職員を代表して、今日の佳き日をお祝いさせて頂きます。そして今日に至るまで、お嬢さま方の学びや生活を支えて来られたご家族、ご関係の皆さまの、長年のご尽力に感謝申し上げますと共に、お嬢様方のご卒業を心よりお慶び申し上げます。
また、御来賓の皆さまには、お忙しい中、ご臨席を賜りまして、卒業生たちをお励まし頂けますこと、まことに有難うございます。今後も、お茶の水女子大学の卒業生の将来を、お見守り頂けますと幸甚に存じます。
今朝、卒業や修了を控えた皆様が、新しくなった正門の門扉の前で写真を撮っていらっしゃる光景に出会いました。あの門扉は、第2次世界大戦の最中に軍によって供出させられて、その後ずっと仮の門扉が取り付けられていたものですが、昨年、卒業生や教職員の方々の念願が叶って、昔の形に復元されたものです。
丁度、以前の門扉とお別れした頃の卒業生の方から、「新しく門扉が復元されて、涙が出るほど嬉しかった」とのお言葉を頂き、私たちも、復元できてよかったと、とても嬉しく思いました。
皆さまは、新たな門扉が復元されてから、記念すべき最初の卒業?修了生です。
皆さまがご参集下さっているこの徽音堂には、日本の国旗と共に、本日卒業?修了の佳き日を迎えられた留学生の方々のお国の旗も掲げてあります。
留学生の皆さまにとって、環境も習慣も異なる日本での生活はとても大変であったろうと思います。お茶の水女子大学を学びの場として選んで下さった方々が、本日、無事に卒業の日を迎えられたことを、心から嬉しく思っています。
母国に戻られて活躍される方もいらっしゃるでしょうし、日本に残って大学院で学ぶ方、就職される方、また日本以外の異なる国に学びの場を求める方もいらっしゃると思いますが、お茶の水女子大学の卒業生として、それぞれの道を、誇りを持って歩んで頂きたいと願っています。
本学は1875年にわが国初の女性のための高等教育機関として国によって設立されてから、140年余りにわたって、社会を牽引する優れた女性達を育て、多様な教育?研究の実績を基盤とする特色ある学問を創成して、平和で公正な社会の発展に貢献して参りました。
長い歴史の中で、本学からは、数多くの優れた卒業生が羽ばたき、国の内外で活躍して参りました。そして現在も、社会の様々な領域で活躍している女性たちと出会ったとき、その多くが本学や本学の附属学校の出身者であることに、驚かされることも少なくありません。
皆さまも、卒業後に、いろいろな場で先輩たちにお会いになることも多いと思います。そんな時、臆することなく「お茶の水の卒業生です」と、声を掛けて下さい。先輩たちは、後に続く皆さまを力強く後押しして下さることでしょう。
因みに、在学中に奨学金や賞を受けられてご存知の方も少なくないと思いますが、本学の同窓会「桜蔭会」では、素晴らしい先輩たちが、卒業生のネットワークを通じて、若い方々の活躍を支援して下さっています。
皆さまが入学されてからの4年間に、本学は様々な記念の年を迎えました。一昨年度には創立140周年を迎え、昨年度には附属幼稚園の創立140周年、そして今年度には附属中学校の創立70周年を迎えました。それぞれの記念式典や記念行事には、各界から多数の皆さまがご列席下さり、共にお祝い下さいました。
こういった周年行事は、わが国の幼児教育から大学院教育までの幅広い教育と研究において、本学が果たしてきた役割の大きさと、その中で若い学生さんたちと共に努力することができる幸せを実感することができた、素晴らしい機会となりました。
今年度は、また、フランス?ストラスブール大学との交流15周年と、アフガニスタン女子教育支援15周年を迎えた年でした。いずれも、15年という節目に当たって、これまでの歩みを振り返り、またこれからの活動のあり方を考えるために、ストラスブールと本学に於いてシンポジウムを開催しました。
2002年に締結されたストラスブール大学との交流協定を起点として、本学とフランスとの交流が盛んになりました。駐日フランス大使館の協力も得て、フランスの様々な大学との間で共同して博士研究指導を行って学位を授与する「共同博士課程」も開始され、本学とフランスの大学から学位を取得した卒業生達は、今、国境を越えて活躍しています。 そして、毎年、学部学生や大学院生がストラスブール大学をはじめとするフランスの大学に留学し、また、研究者の相互派遣が実施され、教育や研究において成果を挙げています。
なお現在、本学では、26カ国74の大学との間で交流協定を結んで、学生?院生?研究者の学術交流を盛んに行っていますので、卒業生の皆さまの中には、これらの制度を利用して、留学された方も多いのではないかと思います。
アフガニスタン女子教育支援事業では、長年にわたる紛争によって社会経済システムや教育システムが破壊されたアフガニスタンの女子教育の建て直しのために、文部科学省、JICA、外務省などのご助力を得て、留学生の受け入れ、教員や教育行政関係者の研修など、様々な活動を続けて参りました。困難な事業でしたから、とても本学独自で実施することは出来ませんでしたので、当時の本田和子学長が、津田塾大学、東京女子大学、日本女子大学、奈良女子大学の学長の皆さまに呼びかけて「五女子大学コンソーシアム」を結成し、その後、紆余曲折はありましたが、15年間に亘って活動を続けて参りました。
昨年11月29日に開催された公開シンポジウムには、多くの関係者の方々のご参加を得て、ご講演やご挨拶を頂き、また、五つの女子大学で修士号や博士号を取得し、祖国に戻って大学教員として活躍している留学生たちのビデオレターの披露がありました。 この事業を通じて、遠いアフガニスタンから本学や4つの女子大学に留学して来た女性たちが立派に成長して、現在、母国の女子教育のために力を発揮している様子を知って、胸が熱くなる想いでした。
彼女たちの凛とした姿を見て、また意欲溢れる言葉を聴いて、この事業を開始した際に初めて本学に来られた若い女性の姿と言葉を思い出しました。その方は「私たちの祖国は、戦乱で荒廃し、女性のための教育システムがすっかり破壊されてしまいました。私たちは今、日本の皆さんに、女子教育の建て直しのための様々なご支援をお願いしています。でもいつの日か、私たちは祖国の教育を建て直し、女性のための高等教育も完備したいと願っています。その日が来たならば、日本の方たちに、是非、見学にいらして頂きたいと思っています。」とおっしゃったのです。その方の願いは、今どこまで進展しているのでしょうか。まだまだ道のりは遠いと思いますが、その中で、留学生たちのビデオレターからは、復興の兆しを感じることができました。
この事業の下、本学では、これまでに修士号取得者7名、博士号取得者2名を輩出するこ